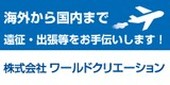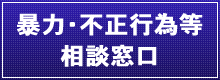

その他
【報告】2025年第3回『JUFAREFEREESELECTSEMINAR』
2025/09/01
8月25日(月)に2025年 第3回 『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』をオンラインにて開催いたしました。
全日本大学サッカー連盟(JUFA)審判部会では、継続的な学生審判員の育成を目的に、これまで本連盟主催の各種大会にて審判割当を行ってきた全国各地域の学生審判員を『JUFA REFEREE SELECT』として招集し、オンラインにて定期的なセミナー(『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』)を開催しています。
今回のセミナーでは、これまで継続的に実施している各地域内での活動報告をまず行い、その後、試合映像をもとにした映像クリップディスカッションを実施しました。


映像クリップディスカッションではオフサイドの判定がテーマとして取り上げられ、特に得点に関わるオフサイド判定に焦点を当ててディスカッションを行いました。オフサイドの判定を行う上で主審と副審の協力関係は他のファウル等のジャッジ以上に必要不可欠なものです。
得点が関わるオフサイド判定において、ボールがゴールインしてからのフラッグアップは試合に大きな影響を与えます。そのような場面が実際に起きた時にどのように対応するのかを審判チームとして試合前の打合せ等で確認しておくことが必要であると指導が行われました。具体的に副審がどのタイミングでフラッグアップを行うのか、得点を認めるべきではないと判断しうる情報をどのように主審に伝達するのかを整理しておくことが求められます。
また、副審からのフラッグアップであったり、選手から確認を求められたことによって主審と副審が判定について協議を行うことは、判定に対する納得感を薄れさせてしまうリスクがあります。そのため、必ずしも常に主審と副審が協議を行うことが判定をする上で最善策かというとそうではなく、協議を行うことが必要な場面であるか、不要な場面であるかをその時の状況により審判は適切に判断し決断していかなくてはなりません。
一方で最終的なジャッジをするのは主審の役割ではあるものの、オフサイドの判定には副審にしか判断できない要素がいくつかあるのもまた事実です。オフサイドポジションにいるかどうかという基準だけではなく、オフサイドポジションにいる選手が他の競技者のプレーにインパクト(影響)を与えたか否かについてもインパクトの要件に沿って適切に判断をしていくことが求められます。
主審、副審、第4審とそれぞれの役割に与えられた任務を再確認するとともに、審判チームとして、状況に応じた適切な連携を図ることが、より精度の高い納得感のある判定に繋がるという事を確認しました。
今後も継続的な学生審判の育成を目的に、様々なテーマのもと定期的なセミナーを開催していきます。
【インストラクターからのコメント】
赤阪修 全日本大学サッカー連盟審判部会員
総理大臣杯(2025年度 第49回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント)の開幕を数日後に控え、参加審判員およびJUFA REFEREE SELECTによる定例会を開催しました。東京都サッカー協会審判委員長の蒲澤淳一氏にもオブザーバーとしてご参加いただきました。まず、夏季期間中の各地域大学連盟での活動状況を共有し、その後、オフサイドに関するシーンについてディスカッションを行いました。主審と副審の役割を明確にし、それぞれの立場で何が「見えて」、何が「見えない」のかを整理したうえで、最終的な判定は主審が責任を持つことを改めて確認しました。「形だけ」の確認や相談は、チームに不安を与えかねず、フットボールの楽しさを損なう可能性があります。自分の役割を明確にし、自分の判断に責任を持って取り組むことが、結果的に納得感の高いゲームを作り上げるのではないかと考えています。JUFA REFEREE SELECT一同、最高の準備をして総理大臣杯に臨むことを確認しました。
【審判員からのコメント】
野母光 2級審判員(九州大学サッカー連盟/西九州大学)
今回の研修では、オフサイドについて、また、副審の役割について改めて学ぶことができました。得点が大きく絡む場面でのオフサイドは、副審との協力の必要性また主審の判断力が試されると思います。事前の打ち合わせにおける副審との対応の仕方などについて見直し、円滑に試合が行えるようにしたいと思いました。副審との協議には、選手の納得感を薄れさせ、主審に対しての不信感を持たせてしまうリスクがあることを認識することができ、協議が必要であるのかないのかを主審自身がしっかり判断することが必要であることを学びました。また、副審を行う際、オフサイドの判断は重要になってくるものであるため、オフサイドに関する要件について改めて整理することができ、これからの活動に生かしていきたいと感じました。今回の研修での学びを生かし、選手たちにとって納得感のある判定を目指し、選手たちが精一杯プレーできるような良い試合環境を作れるようにしていきたいです。
全日本大学サッカー連盟(JUFA)審判部会では、継続的な学生審判員の育成を目的に、これまで本連盟主催の各種大会にて審判割当を行ってきた全国各地域の学生審判員を『JUFA REFEREE SELECT』として招集し、オンラインにて定期的なセミナー(『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』)を開催しています。
今回のセミナーでは、これまで継続的に実施している各地域内での活動報告をまず行い、その後、試合映像をもとにした映像クリップディスカッションを実施しました。


映像クリップディスカッションではオフサイドの判定がテーマとして取り上げられ、特に得点に関わるオフサイド判定に焦点を当ててディスカッションを行いました。オフサイドの判定を行う上で主審と副審の協力関係は他のファウル等のジャッジ以上に必要不可欠なものです。
得点が関わるオフサイド判定において、ボールがゴールインしてからのフラッグアップは試合に大きな影響を与えます。そのような場面が実際に起きた時にどのように対応するのかを審判チームとして試合前の打合せ等で確認しておくことが必要であると指導が行われました。具体的に副審がどのタイミングでフラッグアップを行うのか、得点を認めるべきではないと判断しうる情報をどのように主審に伝達するのかを整理しておくことが求められます。
また、副審からのフラッグアップであったり、選手から確認を求められたことによって主審と副審が判定について協議を行うことは、判定に対する納得感を薄れさせてしまうリスクがあります。そのため、必ずしも常に主審と副審が協議を行うことが判定をする上で最善策かというとそうではなく、協議を行うことが必要な場面であるか、不要な場面であるかをその時の状況により審判は適切に判断し決断していかなくてはなりません。
一方で最終的なジャッジをするのは主審の役割ではあるものの、オフサイドの判定には副審にしか判断できない要素がいくつかあるのもまた事実です。オフサイドポジションにいるかどうかという基準だけではなく、オフサイドポジションにいる選手が他の競技者のプレーにインパクト(影響)を与えたか否かについてもインパクトの要件に沿って適切に判断をしていくことが求められます。
主審、副審、第4審とそれぞれの役割に与えられた任務を再確認するとともに、審判チームとして、状況に応じた適切な連携を図ることが、より精度の高い納得感のある判定に繋がるという事を確認しました。
今後も継続的な学生審判の育成を目的に、様々なテーマのもと定期的なセミナーを開催していきます。
【インストラクターからのコメント】
赤阪修 全日本大学サッカー連盟審判部会員
総理大臣杯(2025年度 第49回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント)の開幕を数日後に控え、参加審判員およびJUFA REFEREE SELECTによる定例会を開催しました。東京都サッカー協会審判委員長の蒲澤淳一氏にもオブザーバーとしてご参加いただきました。まず、夏季期間中の各地域大学連盟での活動状況を共有し、その後、オフサイドに関するシーンについてディスカッションを行いました。主審と副審の役割を明確にし、それぞれの立場で何が「見えて」、何が「見えない」のかを整理したうえで、最終的な判定は主審が責任を持つことを改めて確認しました。「形だけ」の確認や相談は、チームに不安を与えかねず、フットボールの楽しさを損なう可能性があります。自分の役割を明確にし、自分の判断に責任を持って取り組むことが、結果的に納得感の高いゲームを作り上げるのではないかと考えています。JUFA REFEREE SELECT一同、最高の準備をして総理大臣杯に臨むことを確認しました。
【審判員からのコメント】
野母光 2級審判員(九州大学サッカー連盟/西九州大学)
今回の研修では、オフサイドについて、また、副審の役割について改めて学ぶことができました。得点が大きく絡む場面でのオフサイドは、副審との協力の必要性また主審の判断力が試されると思います。事前の打ち合わせにおける副審との対応の仕方などについて見直し、円滑に試合が行えるようにしたいと思いました。副審との協議には、選手の納得感を薄れさせ、主審に対しての不信感を持たせてしまうリスクがあることを認識することができ、協議が必要であるのかないのかを主審自身がしっかり判断することが必要であることを学びました。また、副審を行う際、オフサイドの判断は重要になってくるものであるため、オフサイドに関する要件について改めて整理することができ、これからの活動に生かしていきたいと感じました。今回の研修での学びを生かし、選手たちにとって納得感のある判定を目指し、選手たちが精一杯プレーできるような良い試合環境を作れるようにしていきたいです。