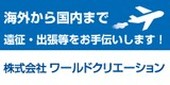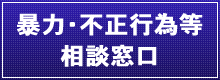

その他
【報告】2025年第1回『JUFAREFEREESELECTSEMINAR』
2025/05/02
4月24日(木)に2025年 第1回 『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』をオンラインにて開催いたしました。
全日本大学サッカー連盟(JUFA)審判部会では、継続的な学生審判員の育成を目的に、これまで本連盟主催の各種大会にて審判割当を行ってきた全国各地域の学生審判員を『JUFA REFEREE SELECT』として招集し、オンラインにて定期的なセミナー(『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』)を開催しています。
今回のセミナーでは、『第39回デンソーカップチャレンジサッカー 静岡大会(以下「デンソーカップ」)』の振り返りがメインテーマとなりました。

今年1回目の開催ということもあり、まず初めに各審判員が所属しているそれぞれの地域における審判関連の取り組みについて近況報告が行われました。各地域共通で行われているような活動内容だけではなく、他の地域では行われていないような独自の取り組みをしている地域活動も報告され、学びの機会となりました。他地域での取り組みを参考にして自地域の取り組みに活かすことが大学サッカーに関わる審判員全体のレベルアップに繋がります。
その後は2月から3月にかけて開催されたデンソーカップについての振り返りが行われました。大会期間中は、参加チームの選手・スタッフと同様に担当審判員及びインストラクターも寝食をともにしながらの宿泊研修型として活動をしましたが、「大会を通して審判員の良い面が多々見られた一方で、生活面や大会に臨む姿勢に個々の意識の差が感じられた」と青山健太インストラクター(全日本大学サッカー連盟 審判部会長)より総括がなされ、赤阪修インストラクター(全日本大学サッカー連盟 審判部会員)からは、「全国の学生審判員の中から選抜された審判員である『全日本大学サッカー連盟選抜審判員』としての自覚と責任を強く持ち、日々の取り組みからより高い意識を持って活動して欲しい」と指導が行われました。
クリップ映像分析では、2つの素材をもとにグループディスカッションを行いました。
1つ目の映像では、タックルの見極めがテーマとして取り上げられました。審判員は、しばしば事象分析をする際にポジショニングやカードの提示方法など具体的な部分に集中してしまう傾向がありますが、それと同時にレフェリーとしてゲームをどのような方向に進めていきたいのか、サッカーというスポーツが何を求めているのかという抽象的な部分を意識することが大事であり、抽象的な部分をしっかりと理解した上で具体的な部分の事象分析をする重要性が確認されました。
2つ目の映像では、キックオフ時におけるレフェリーのプレゼンス(存在感)がテーマとして取り上げられました。レフェリーは試合前のフィールドインスペクションから試合開始直前、試合後まで常に多くの人に見られる存在です。そのため、試合中のみならず試合前、試合後に至るまで選手やスタッフ、観客からの信頼を得られるような身だしなみや話し方など、立ち振る舞いを常に意識することがレフェリーとしてのプレゼンス(存在感)を高めることにも繋がると指導が行われました。
今後も継続的な学生審判の育成を目的に、様々なテーマのもと定期的なセミナーを開催していきます。
【インストラクターからのコメント】
大柿拓馬 全日本大学サッカー連盟審判部会員
2025年第1回目のJUFA REFEREE SELECT SEMINARをオンラインにて開催しました。2段構成の内容で、冒頭の各地域の活動報告においては、それぞれがそれぞれで積極的に活動し、地域ごとの成果や課題などを共有しました。続いての映像クリップを用いたディスカッションにおいては判定時の考慮ポイント、なぜ警告なのか、どのように対応すればよかったのかを整理し、各自の考えや対応などを積極的に議論し発表をしておりました。今後の事業に向けて、限られたチャンスをどれだけものにできるか、そのために必要な取り組みは何かということを、大会と大会の間でそれぞれが考えて取り組むことを確認しました。
【審判員からのコメント】
岩佐丈 2級審判員(東北地区大学サッカー連盟/仙台大学)
全国から集まった審判員、インストラクターの方々から刺激を受けた研修会でした。
「第39回デンソーカップチャレンジサッカー 静岡⼤会」を振り返った後、試合映像を用いてディスカッションをする中で、互いの審判に向かう情熱を再確認できました。
また、「サッカーが求めていること」への考えを深める機会にもなりました。今後の各種大会への準備はもう始まっているという意識を持ち、審判員一同、気を緩めることなく活動を続けて参ります。
全日本大学サッカー連盟(JUFA)審判部会では、継続的な学生審判員の育成を目的に、これまで本連盟主催の各種大会にて審判割当を行ってきた全国各地域の学生審判員を『JUFA REFEREE SELECT』として招集し、オンラインにて定期的なセミナー(『JUFA REFEREE SELECT SEMINAR』)を開催しています。
今回のセミナーでは、『第39回デンソーカップチャレンジサッカー 静岡大会(以下「デンソーカップ」)』の振り返りがメインテーマとなりました。

今年1回目の開催ということもあり、まず初めに各審判員が所属しているそれぞれの地域における審判関連の取り組みについて近況報告が行われました。各地域共通で行われているような活動内容だけではなく、他の地域では行われていないような独自の取り組みをしている地域活動も報告され、学びの機会となりました。他地域での取り組みを参考にして自地域の取り組みに活かすことが大学サッカーに関わる審判員全体のレベルアップに繋がります。
その後は2月から3月にかけて開催されたデンソーカップについての振り返りが行われました。大会期間中は、参加チームの選手・スタッフと同様に担当審判員及びインストラクターも寝食をともにしながらの宿泊研修型として活動をしましたが、「大会を通して審判員の良い面が多々見られた一方で、生活面や大会に臨む姿勢に個々の意識の差が感じられた」と青山健太インストラクター(全日本大学サッカー連盟 審判部会長)より総括がなされ、赤阪修インストラクター(全日本大学サッカー連盟 審判部会員)からは、「全国の学生審判員の中から選抜された審判員である『全日本大学サッカー連盟選抜審判員』としての自覚と責任を強く持ち、日々の取り組みからより高い意識を持って活動して欲しい」と指導が行われました。
クリップ映像分析では、2つの素材をもとにグループディスカッションを行いました。
1つ目の映像では、タックルの見極めがテーマとして取り上げられました。審判員は、しばしば事象分析をする際にポジショニングやカードの提示方法など具体的な部分に集中してしまう傾向がありますが、それと同時にレフェリーとしてゲームをどのような方向に進めていきたいのか、サッカーというスポーツが何を求めているのかという抽象的な部分を意識することが大事であり、抽象的な部分をしっかりと理解した上で具体的な部分の事象分析をする重要性が確認されました。
2つ目の映像では、キックオフ時におけるレフェリーのプレゼンス(存在感)がテーマとして取り上げられました。レフェリーは試合前のフィールドインスペクションから試合開始直前、試合後まで常に多くの人に見られる存在です。そのため、試合中のみならず試合前、試合後に至るまで選手やスタッフ、観客からの信頼を得られるような身だしなみや話し方など、立ち振る舞いを常に意識することがレフェリーとしてのプレゼンス(存在感)を高めることにも繋がると指導が行われました。
今後も継続的な学生審判の育成を目的に、様々なテーマのもと定期的なセミナーを開催していきます。
【インストラクターからのコメント】
大柿拓馬 全日本大学サッカー連盟審判部会員
2025年第1回目のJUFA REFEREE SELECT SEMINARをオンラインにて開催しました。2段構成の内容で、冒頭の各地域の活動報告においては、それぞれがそれぞれで積極的に活動し、地域ごとの成果や課題などを共有しました。続いての映像クリップを用いたディスカッションにおいては判定時の考慮ポイント、なぜ警告なのか、どのように対応すればよかったのかを整理し、各自の考えや対応などを積極的に議論し発表をしておりました。今後の事業に向けて、限られたチャンスをどれだけものにできるか、そのために必要な取り組みは何かということを、大会と大会の間でそれぞれが考えて取り組むことを確認しました。
【審判員からのコメント】
岩佐丈 2級審判員(東北地区大学サッカー連盟/仙台大学)
全国から集まった審判員、インストラクターの方々から刺激を受けた研修会でした。
「第39回デンソーカップチャレンジサッカー 静岡⼤会」を振り返った後、試合映像を用いてディスカッションをする中で、互いの審判に向かう情熱を再確認できました。
また、「サッカーが求めていること」への考えを深める機会にもなりました。今後の各種大会への準備はもう始まっているという意識を持ち、審判員一同、気を緩めることなく活動を続けて参ります。